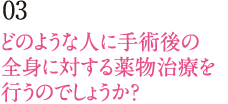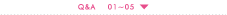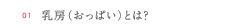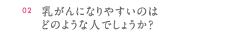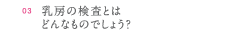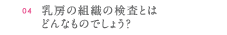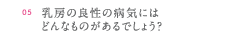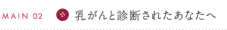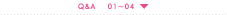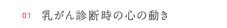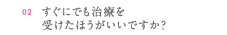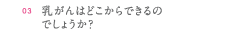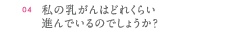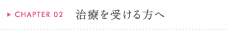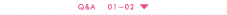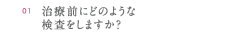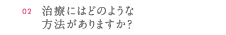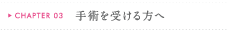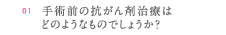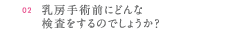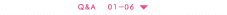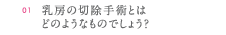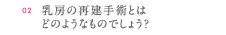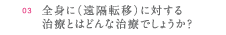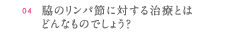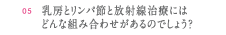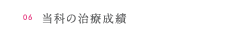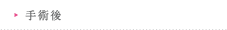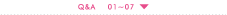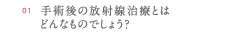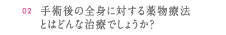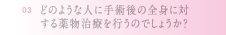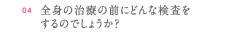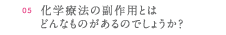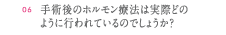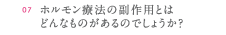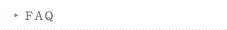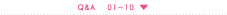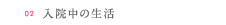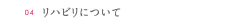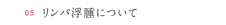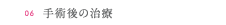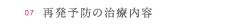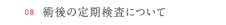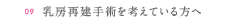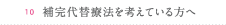どのような人に手術後の全身に対する薬物治療を行うのでしょうか?
どのような症例に術後補助療法を行うのか?
術後補助療法を行う上で、どのような症例に行うのか、その判断材料になるのが、(1)腋窩リンパ節への転移状況、(2)ホルモン反応性の有無、(3)HER2蛋白の有無、(4)腫瘍のサイズ、(5)組織学的悪性度、(6)がん細胞の増殖指数、(7)腫瘍周囲のリンパ管や血管へのがん細胞の入り具合 (脈管浸潤度)、(8)ご本人の希望などで、ご本人希望以外の因子は、切除された標本を顕微鏡で観察し、病理学的に判断します。これらの因子を総合的にみて、術後補助療法の必要性を検討します。100人の患者さんがいれば、100通りの乳癌の特徴とそれに見合った100通りの治療法があります。
| (1) | 腋窩リンパ節への転移状況:すべての乳癌が、腋窩リンパ節を通って全身に広がるわけではありませんが、腋窩リンパ節への転移状況を見ることで、全身への広がり具合を判断する重要な目安になります。 |
| (2) | ホルモン反応性の有無:乳癌細胞の表面に、女性ホルモンと反応する受け皿(受容体)を持っている乳癌(ホルモン反応性)と、持っていない乳癌(ホルモン非反応性)があります。この受容体には、エストロゲン受容体(ER)と、プロゲステロン受容体(PR)があります。ホルモン反応性であれば、術後補助療法として、ホルモン療法を行います。上述のように、閉経状況でホルモン環境も変わり、使用する薬剤も変わってきますので、ホルモン反応性の場合は、月経の有無や、採血で血液中の女性ホルモンの量を測定し使用する薬剤を決定します。 |
| (3) | HER2蛋白の有無:HER2蛋白をどれだけ持っているか、0、1+、2+、3+と判定し、0と1+はHER2陰性、3+は陽性です。2+の場合は、HER2遺伝子をもっているかどうかFISH法という検査で確認し、陽性となればHER2陽性と判断されます。いずれの場合も、切除された組織からその情報は得られます。 |
| (4) | 腫瘍のサイズ:触診や超音波、MRIなどの検査で測定した腫瘍のサイズではなく、切除された組織を病理学的に調べ、がんがどれだけ腫瘍周囲の脂肪、血管、リンパ管などに浸潤しているかといった範囲(これを「浸潤径」という)を測定し、浸潤径の大きさで術後補助療法の必要性を検討します。一般的に浸潤径2cm以上の病変は悪性度が高くなります。したがって、触診では大きくても、浸潤径が小さければ術後補助療法は不要なことがあります。 |
| (5) | 組織学的悪性度:組織学的グレードと表現され、わかりやすく言えば、がん細胞の顔つきで、1から3に分類されます。やはり切除された組織を病理学的に検討し、細胞ひとつひとつの不揃いの程度(細胞異型度)、細胞の核のいびつさ、分裂の早さ(核異型度)、周囲の血管、リンパ管への浸潤程度(脈管浸潤の有無)などで判定します。したがって、浸潤径は小さくても、顔つきが悪い転移・再発のリスクが高いような病変であれば術後補助療法が必要なことがあります。 |
| (6) | がん細胞の増殖指数:増殖マーカーの一つであるKi-67の乳癌上の割合を特殊な方法で染色して検査します。一般的にこのマーカーの値が高い方は、たとえリンパ節に転移がなくても、悪性度が高いと報告されています。そこでこの値が高い方も、術後補助療法の検討が必要になります。 |
| (7) | 腫瘍周囲のリンパ管や血管へのがん細胞の入り具合(脈管浸潤度):がんの周りのリンパ管や血管という脈管の中へのがん細胞の入り具合を確認します。乳癌が他の臓器へ転移する場合は、これらの脈管を必ず通ります。このため顕微鏡下で脈管の中にがん細胞が確認されると、転移や再発をする危険性が高くなります。 |
これまでの(1)から(7)までの因子を総合的に判定し、悪性度が高く、全身に転移しやすいと判断された場合は、術後補助療法をお勧めしています。治療するかどうかは、治療によるメリット(再発予防効果がどれくらいあるか)、デメリット(副作用、費用)、(8)のご本人の希望などを勘案し、主治医とよく相談の上、最終的に決定していきます。