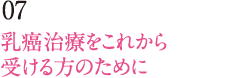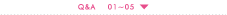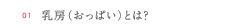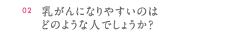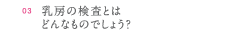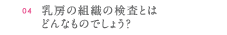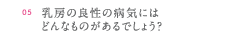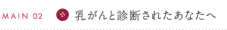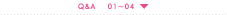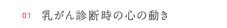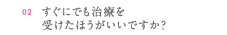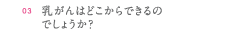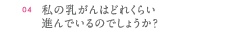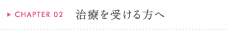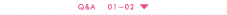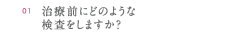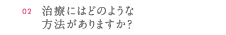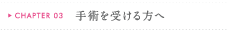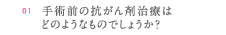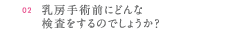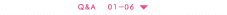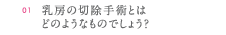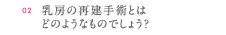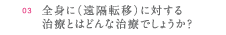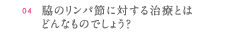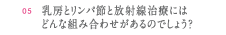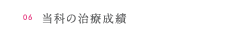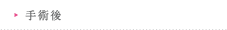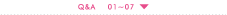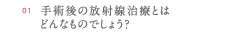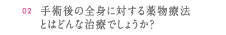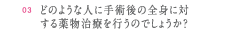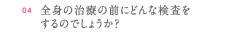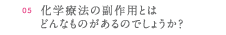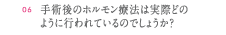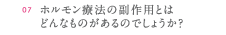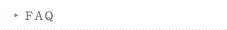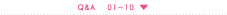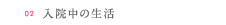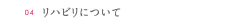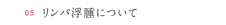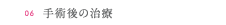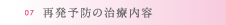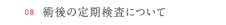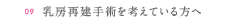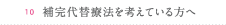再発予防の治療内容
再発予防の治療には大きく分けて、血液の流れに乗って全身に行きわたる薬物療法(抗がん剤治療・ホルモン療法・抗体療法)と、照射をした部分だけに効果がある放射線治療の2つがあります。
■手術後の抗がん剤治療について
どのような人が対象となるのでしょう?
抗がん剤が必要かどうかの目安は、わきの下のリンパ節転移の有無によって判断されます。
リンパ節転移の個数が多いときは、再発予防のために抗がん剤治療が必要になります。
また、リンパ節転移がなくても、「がん細胞の顔つきが悪い」、「ホルモン剤が効かないタイプである」「がんの表面にHER2 という蛋白がたくさんある」「がんがリンパ管や血管の中に入っている」「しこりがとても大きい」「増殖が活発」などに当てはまると、再発の危険がやや高いため、抗がん剤治療をお勧めしています。ただしホルモン治療が有効な方は、抗がん剤を省略できる場合もあります。詳しくは担当医からご説明いたします。
どのような治療でしょう?
再発予防の抗がん剤治療は主に点滴で行います,
抗がん剤の種類によって、毎週点滴するもの、3週間に1回点滴するもの、4週間に2回点滴するものなどがあります。点滴の期間は約3ヶ月〜6ヶ月かかります。これらの治療は外来化学療法室(2階第3診療センター内)で行い、入院で行うことはありません。
どの抗がん剤を使うかは、再発する危険性によって違います。
ホルモン治療や放射線治療が必要なときは、抗がん剤の終了後に行います。
どんな副作用があるのでしょう?
主な副作用は、だるさ、脱毛、吐き気、嘔吐、下痢、便秘、口内炎、味覚の変化、手足や顔の発疹や発赤、手足のしびれ、むくみ、感染に対する抵抗力の低下など非常に多くのものがあります。症状は人によって大きく違い、個人差があり見られない方もいます。
髪の毛は、最初の抗がん剤の点滴から約2週間後に抜け始め、4〜5週間後頃にはほとんど抜けてしまいます。治療を続けている間はうぶ毛の状態が続き、抗がん剤治療が終わればまた生えてきます。治療が終わるとまた生えて来ますが、毛の質や量は治療前と変わる方が多いです。
吐き気については、かなり個人差があります。使う薬によっても違いがあります。抗がん剤点滴の前にはあらかじめ吐き気を予防する薬を点滴します。さらに帰宅後に吐き気止めを内服することである程度抑えることができます。
抗がん剤を点滴すると、その種類にもよりますが、10日〜2週間後に白血球が減って、細菌やウィルスに対する抵抗力が落ちることがあります。白血球はその後目然に 回復して次の点滴までにはもとに戻ります。
閉経前の方は、生理が止まってしまい閉経の状態が続くことがあります。
■手術後のホルモン治療について
どのような人が対象となるのでしょう?
ホルモン治療は、ホルモン感受牲のあるがん(女性ホルモンに反応して大きくなる性質を持つがん)に行います。ホルモン感受性の有無は、切除した腫瘍をよく調べて判定します。ホルモン治療は抗がん剤と比べると副作用が軽い方が多いので、ホルモン剤が効くタイプのがんであれば、再発の危険牲が比較的低い場合でも行うメリットがあります。
どのような治療でしょう?
ホルモン療法は、女性ホルモンをブロックすることにより、がんの増殖を抑えます。
閉経前の方は、がん細胞に女性ホルモンが結合しないようにする薬(抗エストロゲン剤)を5年間毎日内服します、さらに、生理がある方は生理を止める薬(LHRH アゴニスト)を4週間または12週間に1回おなかなどの皮下脂肪の中に注射をします。
閉経後の方でも体内で女性ホルモンが作られています。副腎からアンドロゲンというホルモンが分泌され、これが脂肪組織にあるアロマターゼという酵素によって女牲ホルモンに変換されているのです。このアロマターゼという酵素の働きを止めて、女性ホルモンを抑える薬(アロマターゼ阻害剤)を5年間内服します。
抗がん剤治療が必要な方は、先に抗がん剤治療を終えてからホルモン剤治療を行います。抗がん剤とホルモン剤は同時に使用しません。放射線治療が必要な方は、放射線治療を行いながらホルモン剤を内服します。
どのような副作用があるのでしょう?
更年期症状に似たほてり、のぼせ、突然の発汗などが起こることがあります。また、骨がもろくなったり(骨粗しょう症)、関節がこわばったり痛くなることがあります。
抗エストロゲン剤を長期間内服していると子宮内膜がんになる可能性がやや高くなります。不正出血などがあった場合は担当医にお申し出下さい。また1年に1回の婦人科検診をお勧めしています。
抗がん剤治療に比べるとホルモン剤の副作用は比較的軽い方が多く、脱毛や吐き気、慰染に対する免疫力の低下などはほとんど見られません。
■手術後の抗体治療(ハーセプチン)について
どのような人が対象となるのでしょう?
ハーセプチン治療は、HER2 という蛋白が多くがん細胞に存在する方に行います。がんにHER2 蛋白があるかどうかは切除した腫瘍をよく調べて、HER2 (3+=強陽性)の方が対象となります。HER2 (2+=弱陽性)の方はさらに詳しく調べてハーセプチンが使えるかどうかを決定します。
再発を予防するために使うと再発率を約半分に下げることがわかっています。
どのような治療でしょう?
再発予防で行う場合は、抗がん剤終了後に3週間に1度の点滴を1年間続けます。治療の期間については今後変化する可能牲があります。
どんな副作用があるのでしょう?
抗がん剤治療やホルモン治療と比べるとパーセプチンの副作用は軽いといわれています。
ただし心臓の働きを低下させることがあり、投与前には心臓の機能を調べておく必要があります。初めてハーセプチンを使う場合は発熱や、ごくまれですがショック状態になることがあるため、点滴後2時間ほど病院内で状態を拝見させて頂きます。
■手術後の放射線治療について
どのような人が対象となるのでしょう?
放射線治療は、手術後に乳房または胸壁に残っているかも知れないがんを消失させ局所の再発を予防することを目的としています。
「乳房温存術」を行った方には、残した乳房に放射線治療を行います。乳房温存術でがんがたくさん残っていると考えられるときは、放射線ではなく、再手術(追加切除や乳房切除)をお勧めしています。
「乳房切除術」を行った方で、リンパ節転移が多い方には胸壁などへの放射線治療を行っています。
どのような治療でしょう?
乳房温存手術を行った方は、手術した側の乳房に放射線治療をします。手術した乳房に1日1回週5日を約5週間(計25回)行います。その後、がんがあったところに約1週間追加治療する事が多いです。合計すると約6週間(計30回)かかります。
乳房切除術を行った方の放射線治療は、手術した側の胸全体に1日1回週5日を5週間行います。リンパ節転移が多かった場合は、鎖骨の上などのリンパ節にも同時に照射します。いずれも1回の治療時間は5~10分程度です。
どのような副作用があるのでしょう?
副作用としては、照射した部位の皮膚が赤くなる軽い日焼け、皮膚のかさつき、汗がかきにくい、乳房の軽いはれ、腕やわきの不快感、全身のだるさなどが出ることがあります。ごくまれに、治療後2〜3ヶ月してから放射線による肺炎(咳、発熱)を起こすことがあります。個人差はありますが、一般に副作用は軽く、日常生活に支障を来たすことはほとんどありません。脱毛、吐き気、痛みはありません。